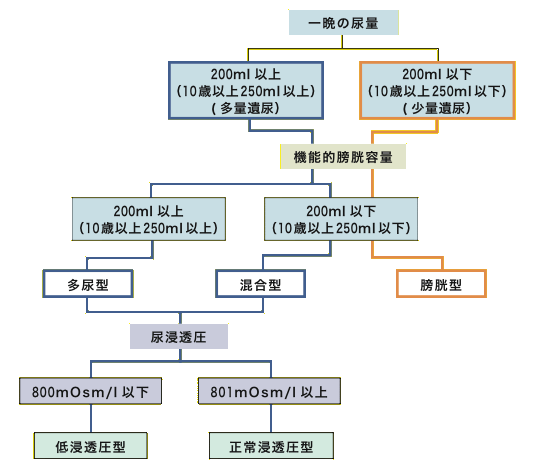| 1)一次性か二次性か 夜尿症は、その状態から一次性(特発性)と二次性に分類されることが多いが、夜尿歴からその いずれかを診断する。筆者の経験によれば、二次性夜尿症は数パーセントにすぎない。 二次性夜尿症は、1年間以上にわたって完全に夜尿が消失したにも関わらず、何らかの契機に よって再び遺尿をみたものである。尚、夜間中途覚醒の結果、見かけ上は夜尿が消失していたと いう場合には、後述するように「トイレおねしょ」の状態とみて、まだ完治していないと考えるべきである。 従って、中途覚醒によってみかけ上夜尿が消失していたのに、再び夜尿がはじまったという場合には、 一次性夜尿と考えている。これらを除外すると、結果的に二次性夜尿症は少なく、数パーセントに 過ぎない。 二次性夜尿症は、心理環境的な影響によるものが多く、まれに尿路感染症、尿崩症(中枢性・腎性) 等によるものがあることにも留意する必要がある。また、夜尿に随伴する頻尿や昼間遺尿、あるいは 遺糞(漏便)などの有無についても、聴取する必要がある。 |
| 2)問診表 夜尿症児への問診表(夜尿症質問紙)を表1に示す。これにて、治療や生活指導の参考となる 夜尿症の状態と随伴する症状を大まかに把握することができる。 |
| 3)夜尿状態の家庭における把握 夜尿症の類型診断を進めていくためには、夜間の尿量、夜間の尿浸透圧(尿比重)、機能的最大膀胱 容量、日中の排尿回数、昼間遺尿の有無について確認する必要がある。 これらの情報を得るために、家庭において1週間にわたって、表2にもとづく記録をつけてもらう必要が ある。 夜間の尿量は、就眠前に排尿した後おむつを着用し、起床時におむつ尿量(元の重量を差し引く)と 起床時尿量を測定し、その合計をもって夜間尿量とする。 夜間の尿浸透圧(尿比重)は、夜間の2〜3時頃に強制覚醒させ、採尿した部分尿の浸透圧(比重)を 測定して判断する。 機能的膀胱尿量は、学校から帰宅後、尿意を感じた際にぎりぎりまで排尿を抑制(がまん)させ、その 際の最大尿量を記録する。起床時尿量が抑制時の尿量より多い場合には、それをもって機能的膀胱 容量とする。 日中の排尿回数や昼間遺尿の有無についても記録してもらう。 これだけの情報があれば、機能的最大膀胱容量(がまん尿あるいは起床時尿量の最大値)、夜間の 尿量、夜尿頻度、尿浸透圧を把握することが可能である。 これらの情報をもとに表3による類型診断基準を参考に類型診断を行う。 |
| 4)一般検査 一般検査としては、検尿(尿沈渣を含む)は必須である。 薬物療法を行う前に血算や生化学検査によって貧血、肝・腎機能等が正常であることを確認する。 薬物療法による副作用の有無を判断するために必須である。 毎晩の昼間遺尿を伴う場合は、潜在性二分脊椎の有無や脊髄の障害等を確認するための腰椎部の X線検査やMRI検査、あるいは、起床時はもとより日中の尿浸透圧が低値の場合、中枢性尿崩症を 鑑別するための精密検査等が必要となる。 |
| 5)類型診断 夜尿症の類型診断に当たっての基準を表3に示す。家庭における記録や尿浸透圧等のデータを 参考に、これらの類型診断を行っていく際のフローチャートを図2に示す。 |