| ● おねしょの生活指導 ● |
| おねしょの治療にとって、生活指導はとても大切です。 まず「おこさず・あせらず・しからず」の3原則を守りましょう。 |
 |
 |
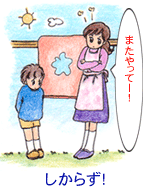 |
| そのうえで、次の生活指導を守ってください。 |
| 幼児期における生活指導 |
| 学童期における生活指導 |
|
|
| ● おねしょの治療 ● |
| おねしょの薬 |
幼児期にみられるおねしょの場合は、まだ発達途上なので、生活指導はつぎのことに 留意するだけで大丈夫です。薬での治療は、まだ必要ありません。 ● 「おこさず・あせらず・おこらず」の基本的な生活指導を守りましょう。 ● 水分は、朝と昼に多めに与えて、夕方からの水分を控えめにしましょう。 ● 日中のおしっこは、もじもじしたからといってすぐうながさず、こころもち膀胱に ためてから行かせるようにしましょう。無理にがまんさせる必要はありません。 ● のどごしに、ゴクゴクと飲む習慣があると、ついたくさん飲んでしまいます。 一気飲みの習慣はやめましょう。 |
| UP |
1. 夜間に起こすのをやめよう 夜間に起こしてトイレで排尿させると、朝まで布団を濡らさないこともあります。 でも、これは"トイレおねしょ"なのです。みかけ上は夜尿をしなくなりますが、実際には 睡眠のリズムが乱れて、ぐっしょり型のおねしょを固定してしまうことになるのです。 また、しっかり膀胱にためる習慣ができず、かえっておねしょをこじらせてしまいます。 夜間に起こすことはやめましょう。 |
|
| 2.水分の飲み方をかえよう おねしょがあると、夜間の水分を減らすようにしていることが多いと思います。 でも、夕方からの水分制限を行うだけではなおりません。 意識的に朝と昼に水分を多く飲んで、夕方からの水分を減らすというように、水分摂取リズムを 意識することが大切です。水分摂取量の一日の配分としては、朝から午前中にたっぷり(350~ 400㏄)と摂取させ、午後から多少控え目 (おやつの水分は100㏄) にし、夕方からきびしく制限 (100㏄とし、夕食に汁物や果物はやめ、朝に与えるなど)するのがコツです。 寝る頃に体に水分がだぶつかなくさせることが大切です。 |
|
| 3.排尿抑制訓練 膀胱におしっこを溜められない膀胱型のおねしょには、おしっこのがまん訓練をして おしっこが充分にためられるようにします。帰宅後、尿意を感じた際に、おしっこをぎりぎりまで がまんさせる訓練です。 がまん尿量は、6~7歳で150㏄、8~9歳で200㏄、10歳以上で250㏄以上はためられるように します。 |
|
| 4.冷え症状への対応 冷え症状はおねしょを悪くします。秋から冬におねしょが後戻りしたり、手足が冷たい、しもやけが できやすいといった場合です。 冷え症状を認める場合には、寝る前にゆっくり入浴させ、ふとんをあたためておくと改善します。 浴剤を用いるならば、炭酸浴剤系(花王石鹸のバブ等)が効果的です。 夏季にクーラーをつけて寝たり、扇風機をかけて寝ると、冬季と同じように冷えて夜尿が悪化します。 |
|
| 5.宿泊行事への対応 学校や地域における宿泊行事には、たとえ毎晩のおねしょがあっても必ず参加させましょう。 貴重な集団生活を体験する機会を失ってはいけません。 宿泊行事に参加する際の留意点は以下の通りです。 ●宿泊の際には、最も治療効果のあった薬を用います。 ●他の子に知られないように、そっと夜間に起こしてもらいます。 ●万一失敗していたら、他の子が起きる前に着替えさせてもらいます。 ●一晩に何回もおねしょをする場合は、寝静まってから保健室に移してもらいます。 |
|
| UP |
おねしょの治療薬としては、以下のものがあります。 |
|
| 1. 多尿型 1 )三環系抗うつ剤 多尿型に対する内服薬としては、アナフラニール、トフラニール、トリプタノールがあります。 これらは、抗利尿ホルモンの分泌をうながす作用があります。いずれも就眠前に飲みます。 副作用としては、食欲不振、悪心、嘔吐といった消化器症状と不眠等が代表的で、これらが 見られた場合には直ちに中止します。 2 ) DDAVP点鼻療法・ミニリンメルト内服 うすい尿が多量に出てしまうタイプのおねしょに使われます。これは、就眠直前に酢酸デスモプレシン点鼻薬を点鼻して、鼻粘膜から吸収させる治療です。 最近は、点鼻薬と同一の効能のあるミニリンメルト錠もあります。就寝前に内服すると、夜間尿量が減少して夜尿が止まります。 水分の摂取リズムを守らず、夕方から水分をがぶ飲みしてこの点鼻薬やミニリンメルトを用いると、水中毒症状と いって浮腫(むくみ)、頭痛、極端な場合にはけいれんといった副作用が出るという報告があります。 |
|
 |
|
| 2.膀胱型 膀胱型の内服薬としては、バップフォーとポラキスが代表的です。 お年寄りの尿失禁治療薬として開発された薬で、膀胱を大きくして溜められるおしっこの量を 多くしてくれます。朝食後、就眠前あるいは就眠前に内服します。成人・老人に対する副作用 としては、口渇(口が乾く)、目が乾く、排尿困難等の副作用が報告されていますが、小児に おいては、副作用はほとんど認められておりません。口が渇く、目が乾くという訴えがごく稀に みられます。 その他に、また、ブラダロンとプロバンサインという薬も用いることがあります。 |
|
| 3.混合型 多尿型と膀胱型とが合併している混合型に対しては、この二つのタイプの薬を 併用して治療していきます。 |
|
| なお、幼児期にみられるおねしょに対しては、発達途上にあるので、薬物による治療は必要 ありません。 |
|
| UP |